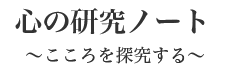nhi.dang
東洋心理学 Psychology
意識場
東洋の心理学を考慮すれば、私たちの意識経験は〈意識の場〉と〈意識内容〉の二つに区別される。意識の場とは「知る」という主観的作用の生じる「ところ」である。それはあらゆる主観的意識事象/クオリアが生じ、踊る「舞台」である。(ここで言うクオリアは、赤さ、音色、芳香、苦み、痛み、喜び、悲しみ、欲求、意志、自我感覚・・・等の意識経験の内容の全てを意味する)
磁力や電力が作用する場が「電磁場」と呼ばれるように、知るというはたらきが作用する場(ところ)が「意識場」である。この「場」の活動の内に、多彩な意識内容/クオリアが生まれる。場の活動状態の変化がクオリアとなる。
東洋心理学の視点から言えば、この場には大きく分けて、二つの活動レベルが存在している。その二つとは、場の〈微細〉なレベルと、〈粗大〉なレベルである。日常生活において私たちが認知しているのは、後者の〈粗大〉な場の活動レベルである。前者の〈微細〉な場の活動レベルは潜在的なものであり、通常、認知されることは無い(図1)。
図1 心の諸性質(三島ジーン「こころを探究する」より引用)
| |
場のレベル |
微細な活動レベル |
粗大な活動レベル |
| 無常相 |
日常相 |
| Ⅰ |
Ⅱ |
Ⅲ |
| 性質 |
知る、場 |
プレクオリア |
スナップショット |
主客二元 |
意味処理
判断、概念 |
| 内容 |
空 |
光
ルーパ・カラーパ |
無常の世界 |
感覚世界 |
意味の世界
論理の世界 |
| 大乗起信論 |
心真如 |
心生滅(三細・六麁) |
| ゾクチェン |
ダン |
ロルパ |
ツァル |
| チベット密教 |
最も微細な
レベル |
微細な
レベル |
粗大な
レベル |
場の微細な活動レベル
普段は隠された微細な場の活動が顕在化する機会(あるいは手段)は、少なくとも二つある。
その一つは「死」を迎える際(臨死)である。死の間際、場の粗大な活動レベルがゆっくりと後退すれば、場の微細な活動レベルは「光」の体験として現れて来る。チベット密教が伝えるところによれば、死のプロセスの進行の程度に応じて、その光の様相は変化する。その変化の度合いは、意識状態の変容の程度を示す指標(死のしるし)となる。死に行く者は、日頃慣れ親しんだ世界(粗大レベル)から、光の世界(微細レベル)へ突入する。
そして、もう一つの微細な場の活動が顕在化する機会(手段)は、極度の注意集中である。仏道では「止観」と呼ばれる注意集中の技法を駆使した瞑想が実践されるが、この止観の行では注意集中した箇所に、「ニミッタ」と呼ばれる特殊な心像が現れて来る。注意集中が深まるにつれてニミッタは、より澄み、光り輝くものへと変貌してゆく。その光の心像の変化の具合は、注意集中の程度を示す指標となる。
熟練した止観の行者は、この澄んで輝く「光」を、非常に微細な場の活動(ルーパ・カラーパと呼ばれる微細な粒子の集団)として認知するようになるが、彼らの指摘によれば、光の世界(場の微細な活動)は、各種の感覚刺激に応答し、多彩なクオリアの世界(場の粗大な活動)へと分化発展しているようである。光の世界は私たちの感覚世界の根底に位置しており、それは成熟なクオリアが分化発展する以前の世界である。
場の粗大な活動レベル
最近の欧米の一部の意識研究者が指摘するように、また、アジアの止観の行者らが古くから伝えて来たように、非常に短い時間スケール(おそらく数十ミリ秒程度以下)においては、私たちの意識経験は映画のコマ(あるいは連続するスナップショット)のような、離散的な在り方をしている可能性がある。私たちが認知する意識世界は油絵のようにべったりとクオリアで塗られているが、止観の行者らが認知する刹那レベルの意識情景は、クオリアの有る瞬間と無い瞬間が分別された無常の世界である。彼らはクオリアの塊ではなく、クオリアの波動を認知する。意識経験は本来、波動性を有しており、水面上に広がる波のように、成熟したクオリアは意識の場上に波動的に展開して行く。
今この瞬間において生起する意識経験の一コマ(スナップショット)、そして既に過ぎ去ったスナップショットの記憶(メモリ)群は統合し、普段私たちが感じているような「今現在の意識シーン」が出来上がる。「今」と「過去」の情報群は混和し、数百ミリ秒程度以上の時間スケールの「今現在の意識シーン」が形成される。
今現在の意識シーンの内で混和した「今」と「過去」の情報群は統合し、そのタイムスケールの中で「主」と「客」の二極の心理学的構造が生まれる(それ以前は主客未分の境地である)。視覚、聴覚、触覚といった感覚情報群は統合し、感覚世界(客体)が仮構される。また、情動、感情、思考、概念化作用、欲求、意志といった精神の作用と、身体の感覚(体性感覚)は統合し、自己の感覚(主体)が仮構される。
この主客二元の心理学的形式の下で、意味処理や概念化作用のプロセスは進む。人間は言語活動によって、その能力は著しく増強されており、そこには高次の意味の世界、概念の世界が構築されている。
自己
私たちの意識経験を意識場(知ること)と意識内容(知られたもの)の二つに分けた場合、心の中心機能である自我(私)は「意識場」と「意識内容」の両方によって仮構されるが、自己感覚の根幹は前者の意識場(知ること)の方にある。自己は常に「知る」というはたらきと共にある。認知の流れの中で『明瞭に』知られたモノは、自己とはならない。自己は常に知る者である。
意識内容を伴わない「場のレベルの本来の自己」は、特定の内容や構造によって条件付けられない。そこにおいて自己は無定形であり、自己は意識内容(知られたもの)によって制限を受けない、純粋な知る者である。しかしながら、意識場の活動〈識〉によって、そこに様々なクオリアが発現するようになれば、知る者は特定の意識内容によって肉付けされ、それは具体的で条件付けられた者へと移り変わる。
身体各所の体性感覚は集束して一つのボディ・イメージ〈色(しき)〉を形成し、自己に物理的基盤、個体としての感覚、同一性、安定性を付与する。そこにはボディ・イメージを基軸にした三次元の空間の感覚と時間の感覚が生まれる。このボディ・イメージという「身体場」の中に、情動・感情〈受〉、思考〈想〉、欲求・意志〈行〉の流れは集束して行く。これら五つの要素(識、色、受、想、行)の活動の総体は、「今現在の意識シーン」の内に、リアルタイムに自己の感覚を仮構する。
日常生活においては、五つの要素(識、色、受、想、行)は健全なバランスを保ち、正常な自己の感覚が形成されている。しかしながら、心理学的条件、神経生物学的条件などによって、このバランスが崩れることになれば、様々なタイプの自己感覚の変容体験(離人症、神秘体験など)が生じることになる。
絶対知(無分別智)
意識場の活動の結果、場には意識の「波動特性」「統合作用」「概念化作用」といった、様々な一般的性質が現れて来る。場はこれらの心の一般的性質群によって構造化、機能化され、日常的な意識経験となる。
しかしながら、これらの心の一般的性質が一掃される「或る特殊な条件」においては、「場」の最も純粋な性質が直知されることになる。その瞬間、心の本性は如実に理解される。この純粋な場のレベルの心は、取られる(認知される)対象と思考から離れた「空(くう)」の状態であり、主客二元の認知構造も消失している。
東洋で言うところの「覚り」とは、この「場」のレベルでの心の本性を、直知することである。心の様々なはたらきが払拭され、心の本性が顕わとなった瞬間、心の本性を知る根本的な智慧、絶対知(無分別智)は訪れる。
>詳細は「文献 References」のページから
▲ページ上部へ戻る